2025年度【第1回合不合判定テスト】が4月6日に迫ってきました。合不合テストは組分けテスト比べますと、
●地理・歴史・公民すべて出題
●【地理】は範囲は読みにくい(2024年合不合の範囲は、【地形と貿易、工業】)
●【歴史】の範囲が広い(基本的には、原始~江戸ですが、1回目は原始時代はあまり出
ない。)
●【公民】は易しめ(理由は【組分けテスト】が細かめだから。範囲は広い。)
といった特色があります。2023年・2024年過去問から【歴史】に関しては「江戸時代の終わり」(1867年大政奉還)までは勉強することがのぞましいでしょう。
春期講習中ということもあり、あれもこれも社会の復習することは困難です。そこで2024年の合不合判定テストでどのような知識が問われているかを見ていこうと思います。
同じ問題は出題されなくとも、基礎的な復習は意味がありますし、出方のパターンには類似性もあります。
時間がない人は解答の黄色蛍光線だけでも確認してみてください。
大問1 地理(地形)に関する問題
●まず、最初に日本地図が大きく書かれ、【地形】の問題がでています。(ちゃんと地図は見ましょう。昨年個別指導していた生徒は地図を見ずに解いてしまい間違えていました。)
●「石狩川」と「上川盆地」のセットを選ぶ問題。(小5の組分けテストでも石狩平野ではなく
上川盆地を出題する傾向が四谷大塚の模試ではよくあります。)
●秋田県の半島は出題→「男鹿半島」
●長野県と山梨県の間の山脈→「赤石山脈」(日本アルプスは位置を把握しておきましょう。
飛騨(ひだ)山脈は富山県と長野県の間です。)
●出入りが複雑な海岸(志摩半島)→「リアス」海岸
●日本標準時は東経135度(明石市を通ることは皆さん知ってますが、京都府の丹後半島も通る
ことを知っておきましょう。)
●地図の場所から瀬戸内海を書かせる問題(なぜか、瀬戸内海の位置がよくわかっていない生徒は多いです。高知県は太平洋側ですが、瀬戸内地方と勘違いしている人が時々います。)
●九州の火山。桜島(鹿児島県)・雲仙岳(長崎県)・阿蘇山(熊本県)→あてはまらないのは有珠山(北海道)(なお、桜島は噴火により大隅半島と結合。雲仙岳は世界最大級のカルデラで有名です。)
●雲仙岳は1990年の噴火により火砕流で死者がでた。四谷大塚の模試は「火砕流」がよく出ることをしっておきましよう。(土石流と区別させる問題が四谷のパターン。土石流は集中豪雨で発生。)
●日本の活火山の数は111(選択肢が、「1000以上」で✕、というひっかけ問題が出題)
●地熱発電は火山まわり。再生可能エネルギー。(大分県の八丁原(はっちょうばる)が有名です。)
●屋久島(鹿児島県)の「形」が出題。島の形をチェックしましょう。
●沖縄の気候や地形→さんごが長い年月をかけて変化した、水はけのよい土地がみられる。
→これが正しい選択肢。(石灰岩、水を保持できない。米づくりに向かない
地形なのが沖縄県です。)
●川の河口を問う問題(水源も調べると格段のレベル差があきます。これは難問)
北上川→河口は宮城県 ※日本で最も長い山脈(奥羽山脈)に降った雨や雪どけ水が流れ込
む川)
信濃川→河口は新潟県 ※日本で最も長い川
利根川→河口は利根川※日本で最も流域面積が広い川
淀川→河口は大阪府 ※日本で最も面積の大きい湖(琵琶湖)から流れ出る川。
上の4つの川から利根川を選び問題。易しいですが、水源と河口はわかっていない生徒が多
いので地図帳を確認しておきましょう。(以上2024年合不合判定テストの地理の大問1)
大問2 地理(【貿易・工業】)に関する問題
●成田国際空港の輸入品の1位~3位→通信機・集積回路以外にもう一つ→「医薬品」(飛行機で運ぶので小さく・軽く・高価なものを考えます。)
●東京港の輸入品の1位~3位→コンピュータ・集積回路以外にもう一つ→「衣類」(東京や大阪は人口が多いので船で衣類を輸入。なかなか重たいです。)
●名古屋港以外で、自動車・自動車部品を輸出している港→「横浜港」(日産自動車を意識しましょう)
●名古屋の自動車輸出が多い理由→どこの工業都市→「豊田市」(トヨタ自動車)
●自動車の組立工場→「プレスし塗装した後に溶接し、部品をとりつける」→✕(塗装と溶接の順序がが逆。「プレス→溶接→塗装→組み立て」の順が正しい。
●自動車の生産台数→中国>ドイツ>アメリカ>日本→✕(中国>アメリカ>日本>ドイツが正しいです。)
●電気自動車は「燃料となる酸素」→✕(電気自動車の燃料は酸素ではなく電気です。酸素と水素を合わせる「燃料電池車」と、電気自動車・ハイブリッドカーの区別を押さえましょう。小5組分けテストでもよく出ております。)
●為替(正答率が低い問題)
日本の自動車会社が海外の工場での生産を増やすときは、ふつう、ドルの価値が円の価値に対して
【 A 】なったときです。
問 Aにはあてはまるのは「高く」か「低く」か?→正解は「低く」
※解説
この問題は昨年間違えた人が多かった問題です。円高・円安だけで考えるとケアレスミスをしてしまいます。日本の会社が「海外の工場での生産を増やす」のは円高だからです。そして円高というのは「ドルの価値が円の価値に対して【低い】状態」です。(円高=ドル安)本問は問題文から「ドル安→円高」を考えなければならないので難問です。
また、このようなとき(円高のとき)、日本では【 B 】なる傾向があります。
問 Bにあてはまるのは、「外国人観光客が多く」か「電気料金が安く」か?→正解は「電気料金が安く」
※解説
この問題は円高の時にどうなるかを考えれば解けます。円高の場合は外国人観光客が少なくなります。なぜなら、円高だと外国人にとって日本への旅行はコスト高となるからです。次に円高なら電気料金は安くなります。なぜなら、電気の原料の天然ガス・石炭・石油のほとんどが輸入品で円高だと安く輸入できるからです。
●原油を運ぶ船を写真で問う問題→タンカーが正解(他に自動車運搬船、液化天然ガスを運ぶLNG専用船、コンテナ船の写真。)
●石油に関する問題
「石油は日本の火力発電で使用する燃料の中で最も多く使用」→✕(火力発電で使用する燃料の中で最も多いのは天然ガスです。石油は自動車燃料のガソリンや石油化学工業の原料のナフサに使用されます。)
「石油化学工業に関連する工場がパイプでつながっているしくみをモーダルシフトという」→✕(モーダルシフトではなくコンビナートが正解。モーダルシフトは二酸化炭素を減らすため、貨物をトラックで全て運ばず、鉄道や船を利用する輸送形態です。鉄道や船は二酸化炭素排出量がトラック(自動車)よりも少ないです。)
「石油から精製されるナフサはセメントなどの多くの化学製品の原料となっている」→✕(セメントの原料は石灰石。ナフサはプラスチックやゴムなど石油化学工業の原料です。)
石油化学工業のさかんな都市には千葉県の市原市などがある→正解(千葉県は化学工業1位。)
●貿易港の特色
・「成田国際空港は海上の埋め立て地に建設された」→✕(埋め立て地に建設されたのは関西国際空港)
「東京港にはポートアイランドがある」→✕(ポートアイランドがあるのは神戸港です。)
「名古屋港は伊勢湾に位置する」→〇(伊勢湾の位置を地図帳で確認しましょう。知多半島の西側)
成田国際空港、東京港、名古屋港、関西国際空港を西から順に並べると、関西国際空港は2番目になる→✕(1番目。西からならべると関西国際空港→名古屋港→東京港→成田国際空港となります。)
●貿易総額の推移のグラフの読み取り
貿易総額の計算は【輸出額+輸入額】を知っておきましょう。(【輸出額−輸入額】とかんちがいしている生徒がいます。)
(以上2024年合不合判定テストの地理の大問2)

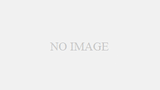
コメント