第6回 「内閣と裁判所」
〇内閣
●内閣の仕事
内閣が締結し国会が承認する仕事→条約
内閣の仕事→憲法や法律に定められていることを実施するために【 】を制定する→政令
天皇の【 】に対して助言と承認を行う→国事行為
●内閣のしくみ
・内閣が総辞職しなければならない国会→衆議院解散後に行われる衆議院議員総選挙の日から30日以内で召集される国会→要するに特別国会のこと
※その他の選択肢
・衆議院・参議院のいずれかで、総議員の4分の1以上の要求があると召集される→臨時国会
・国会と内閣は密接は関連している→このことを何というか?→議院内閣制
※この問題は組分けテストにしては雑ですね。
議院内閣制というのは「内閣が国会に対して連帯責任を負う制度」とおさえましょう。
・法律案を提出することができる者や機関は?→「国会議員(衆議院議員と参議院議員)と内閣」
・内閣総理大臣とすべての国務大臣が全員出席して、行政についての決定を行う会議→閣議
●外局
・内閣の下に置かれている機関
Ⅰ 情報通信や選挙などの仕事→総務省
Ⅱ 観光や気象に関する仕事→国土交通省
●民営化
・「電話事業」「郵政事業」「鉄道事業」「たばこ事業」のうち2000年以降に民営化された仕事として正しいもの→正解は「郵政事業」
●公務員
第15条 「すべて公務員は全体の【 】であって、一部の【 】ではない」→奉仕者
・「東京都庁の職員」「新宿区役所の職員」「会計検査院の職員」「横浜市役所の職員」のうち、地方公務員として正しくないもの→「会計検査院の職員」(この職員は国家公務員)
〇裁判所
●裁判所(その1)
・全国に8か所あり、多くの裁判の第2審が行われます。→高等裁判所
・全国に50か所あり、少年法にもとづく少年犯罪の審判を行います。→家庭裁判所
ア 最高裁判所 イ 高等裁判所 ウ 地方裁判所 エ 簡易裁判所 オ 家庭裁判所
●裁判所(その2)
・76条3項 すべて裁判官は、その【① 】に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び【② 】にのみ拘束される。
→①良心 ②法律
●裁判員裁判
・裁判員はくじで選ばれます。→〇
・有罪であればどのような罰をあたえるかを決めます。→〇
・民事裁判は行われません。→〇(重大な刑事裁判のみ)
・裁判員裁判では控訴が認められていません。→✕(控訴できる)
●刑事裁判と民事裁判
Ⅰ 訴えられた方はふつう弁護士をつけます→刑事裁判・民事裁判両方あてはまる
Ⅱ 検察官が被疑者を起訴します→刑事裁判のみ
第7回 【国と地方の政治】
〇三権分立
国民審査の対象となる裁判官→最高裁判所のみ
●政治や社会の問題に対する多くの国民によって、内閣は政策を変更したり、ときには内閣が総辞職したりすることがあります。このような国民の意見のことを何というか?→世論
●三権分立の目的
三権分立のしくみを政治に取り入れることは【 】を守ることにつながります。→【 】は基本的人権である。
※「三権分立」というのは権力を3つに分け相互に監視させることで「権力の暴走を防ぐ」ことです。
権力の暴走を防ぐことで国民の「基本的人権」が守られます。
●三権分立の内容
・国務大臣は内閣総理大臣によって【 】されます→任命
・最高裁判所の長官は、天皇によって【 】されます→任命
・最高裁判所の長官は、内閣によって【 】されます→指名
・最高裁判所の長官以外の裁判官は、内閣によって【 】されます→任命
〇地方の政治
●公共サービスを選ぶ問題
上下水道の整備・電気の供給・消防・警察→このうち公共サービスではないものは電気の供給です。(電気の供給は民間の仕事)
●国民が国と地方に納める税金の合計は100兆円を超えている→〇
地方交付税交付金は国が地方公共団体から渡されるお金です→✕(国が地方公共団体に渡すお金)
公共事業関係費よりも、介護給付費の方が金額が金額が多くなっています→✕(公共事業関係費>介護給付費)
〇地方の政治
・地方議会は二院制です→✕(地方議会は一院制である。)
・地方議会は出席議員の過半数の賛成で首長を不信任できます→✕(首長の不信任には地方議会議員の4分の3の賛成が必要です。)
・首長は地方議会の議員から選ばれます→✕(首長を選びのは地方議会の議員ではなく、住民です。8直接選挙)
・首長は地方議会に議決のやり直しを求めることができる→〇
〇選挙
●衆議院選挙について
・小選挙区選挙では、全国を289の選挙区に分けて、それぞれの選挙区から1名ずつ選出されま
す。→〇(衆465人中289人が小選挙区から、176人が比例代表区から当選します。小選挙区は
289ブロックで、比例代表区は11ブロックです。)
・比例代表選挙では、政党が事前立候補者に順位をつけた名簿を届け出ます。→〇(拘束名簿式といいます。)
・小選挙区でも比例代表でも、議員1人あたりの有権者数に大きな差が生じてしまうことがある→✕
・小選挙区の選挙では、比例代表の選挙と比べて落選者に投ぜられた票が多くなる傾向にある→〇
(いわゆる死票の問題。)
●参議院議員選挙の選挙区選挙では、複数の都道府県が1つの選挙区となる合区が取り入れられて
いるところがある。このうち高知県と合区になっている都道府県はどこか?→徳島県
(人口が少ない「鳥取県・島根県」、「徳島県・高知県」は参議院の選挙区選挙で合区となり2つの県から1人の代表者が選ばれることになった。1票の格差の解消措置の一つです。 )
第8回 社会保障と財政
〇社会保障
●介護保険
・2000年に導入→〇
・介護サービスにかかる費用のすべてを国が負担します→✕(サービスを受ける人は1割負担です)
・介護の認定は市町村が行います→〇
・ホームヘルパーが介護の計画を立てます→✕(介護の計画をたてるのはケアマネージャーです)
●少子化について
①0~14位の人口割合→約11%(高齢者の割合は29%です。)
②少子化対策をおこなう新しい国の役所(2023年から)→こども家庭庁
●収入がなかった少なかったりして生活を送ることがきびい人に対して、生活費や医療費を支給する制度→公的扶助
〇復習範囲
●占領政策
・連合国軍の日本占領は行われるようになったときのGHQno最高司令官の名前→マッカーサー
●政治の民主化
・治安維持法が廃止されました→〇
・アメリカで開かれた軍事裁判で、東条英機が処罰されました→✕(アメリカではなく東京で開かれた)
・日本の軍隊が解散させられました→〇
・昭和天皇が神の子孫であることを発表しました。→✕(天皇の人間宣言により神の子孫であることが否定された。)
●経済の民主化
・日本の経済を支配し、戦争に協力して大きな利益を得ていた企業グループがなくなりました。
この政策を何というか?→財閥解体
●平和主義
・平和主義は日本憲法のどこに示されているか?→「前文・第9条」
・12条~「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の A の B によって、これを保持
しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に C のた
めにこれを利用する責任を負う。」
A 不断 B 努力 C 公共の福祉
・信教の自由を保障するため、国や地方公共団体は、どのような宗教的活動も行ってはいけない原則がとられています。→この原則を「政教分離」という。
・サンフランシスコ平和条約の直後に結ばれた、アメリカ軍が日本国内に留まることを認める条約
→日米安全保障条約(1951年)
・サンフランシスコ平和条約の前年におきた東アジアでのできごと→朝鮮戦争(1950年)
・国際連合の加盟のきっかけとなったできごと→日ソ共同宣言(1956年)
〇財政
●社会保障関係費の中で一番多い支出は【 】給付費です→【 】は年金
●地方の予算の歳入のうち、地方税・地方交付税についで多いもの→国庫支出金
(国庫支出金とは国と地方公共団体が共同で行う仕事に関するお金。使い道が決まっている)
●税に関する問題
①個人の収入にかかる税金→所得税
②税金を2つに分けたとき、負担する人と納める人が同じ税金を何というか→直接税
※直接税~税を納める人と税を負担する人が同じ
間接税~税を納める人と税を負担する人がことなる(税を納める者(納税者)のが「店」で税を負担する者(担税者)が「消費者」です。)
③収入が多くなるほど税率も高くなるしくみ→累進課税
●前回範囲(【第1回 組分けテスト】の範囲)
・

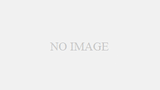
コメント