●憲法改正
国会の発議(衆議院と参議院で各議院の【 A 】と【 B 】の賛成)
↓
【 C 】で国民の承認が必要
↓
天皇が国民の名で憲法改正を【 D 】します。
【A】総議員 【B】3分の3以上 【C】国民投票 【D】公布
●日本国憲法について
・貴族院と衆議院で大日本帝国憲法の改正案が審議され、日本国憲法として制定された。→✕(貴族院が間違い。衆議院のみ。)
・日本国憲法が成立した後、女性の選挙権が認められました→✕(女性の選挙権が先(1945年)日本国憲法の成立(施行)は1947年5月3日)
・日本国憲法は、天皇が国民に授ける形で定められました。→✕(天皇が国民に授ける形は欽定憲法という。日本国憲法は国民が定める民定憲法である。)
・日本国憲法は、前文と103の条文で成り立っています。→〇
●天皇
・天皇は、日本国憲法で「日本国の【 】であり日本国民統合の【 】であると定められています。→【 】は象徴
・天皇の国事行為に助言と承認をあたえる機関の名→内閣が正解
●第【① 】条
…国権の発動たる戦争と、【② 】による威嚇又は【② 】の行使は、国際紛争を解決する手段として永久にこれを放棄する。
→①第【9】条 ②【武力】
●人権
教育を受ける権利・労働者が団結する権利・働く権利・裁判を受ける権利のうち、社会権にふくまれない権利はどれか?→「裁判を受ける権利」
※まず、社会権というのは、社会的に「弱い立場にいる人」を守るための権利です。
この社会的に「弱い立場にいる人」は、
①「高齢者」②「障がい者」③「こども」④「労働者」の4つです。
①「高齢者」~高齢となり体力のおとろえや定年退職して仕事をしていない・できない人もおり
「弱い立場」
②「障がい者」|~けがや病気を抱えるなどの「弱い立場」
③「こども」~母子家庭(父子家庭)など両親がいない場合や両親ともにいないこどもは
「弱い立場」
④「労働者」は「辞めさせられたり」、「給料を下げられたり」する可能性があるので、憲法上特
に保護されています。(「強い立場」は経営者)
このように弱い立場ごとに憲法は次のような社会権を保障している。
①「高齢者」②「障がい者」→生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)
③「こども」→教育を受ける権利(義務教育などの制度を法律で保障している。)
④「労働者」→勤労の権利(働く権利)・労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)
本問の社会権にあたらない権利は、裁判を受ける権利である。裁判を受ける権利は「社会権」ではなく、「請求権」であり主に裁判所に請求する権利である。「弱い立場」に限定されず、「すべての人」に請求権は認められる。
・どんな宗教を信じても、または信じなくてもよい権利が定められ、義務教育の期間は公立の学校で宗教的な行事を行うことが許されています→✕(憲法20条で「何人も宗教上の行事に参加することが強制されない」とある。)
・日本国憲法が定められたころと比べて社会が変化したので、「知る権利」などの新しい人権について定めた条文が追加されました。→✕(知る権利などの新しい人権は条文には追加されていない。裁判所が認めた権利であり、知る権利やプライバシー権があります。条文に追加するのは憲法改正手続きが必要である。)
●日本国憲法と大日本帝国憲法にも「ほぼ同じ内容で義務」として定められているもの→税金を納める義務(納税の義務)
●天皇の章(第1章・1条~8条)で示されている日本国憲法の三大原則→国民主権(1条~「主権の存する日本国民」)
●法律や命令といったほかのすべての法令よりも優先されるきまりに位置づけられるきまり→最高法規

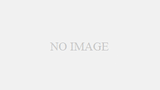
コメント