問1 1 ①は寒流(寒い北部から海流から流れるので寒流。)①は千島海流(親潮)
2 「たら」「さけ」の水揚げ量は北海道(ともに1位)で多く寒流魚を判断できる。
「にしん」は「春告魚(春をつげる魚)」と呼ばれ春に産卵するので寒流魚と推
測できる。よって、暖流にのって移動する魚は「エのかつお」と判断できる。
(かつおは、太平洋に一本釣りでつりにいくことが分かれば赤道に近づくため暖流魚
と推測できる。)
3 潮目に位置する漁港として石巻港(宮城県)と銚子港(千葉県)が有名である。
本問は③の港なので銚子港と判断できる。
問2 1 ④の湾は青森県の陸奥湾なので「アのほたて貝」が正解。
(イの「うなぎは鹿児島県」、ウの「かきは広島県」、エの「のりは佐賀県」
が1位である。)
2 魚付林(うおつきりん)(森林からの豊富な栄養でプランクトンが増え、魚
を増やすことを目的とする。)
3 栽培(漁業)(「稚魚を育てて放流」と「成長した魚をとる」がキーワード。記述で
出題可能性がある。)
問3 1 東シナ海(シナはCHINA(チャイナ→シナ)が語源。チャイナの語源はも
ともとは秦(シン・最初の皇帝が生まれた王朝)といわれている。(中国の東
側にあるので「東シナ海」と呼ばれる。)
2 底引き網(海底付近の「かれい」などを釣る漁法。ときどきイルカもつれ
る。網で魚が傷む可能性があることが近年の【渋幕】で出題されている。)
3 「東シナ海」という日本から遠いわけでなく「数日間」かけて漁を行う漁業は沖合漁業
と判断できる。(沿岸漁業なら「日帰り」、遠洋漁業なら「数か月」かかる。)
沖合漁業はア(漁獲量1位)(2位は養殖業のウ、沿岸漁業は3位でイである)
問4 1 遠洋漁業の漁獲量が減っている理由は1977年に国連海洋法条約で設定された200海里が考え
られる。200海里は「約370km以内の海でしか魚がとれない」ということを各国に認めさせ
た。(1海里は1852mである。)
2 漁業で働く人数というのは暗記するものではない。(なんでもかんでも覚えられない)
第1次産業(農林水産業)の人口は「5%くらい」は知っておきたい知識。とすると、「農業・林
業・水産業」で5%なので水産業は1%くらいと推測できる。日本の人口1.25億人の1%なので、
漁業で働く人の人口は「エの120万人」と判断できる。
3 1990年代ころから日本の経済は低迷し、中国の経済は成長することは知っておこう。
正解は、イの中国である。

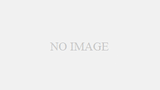
コメント